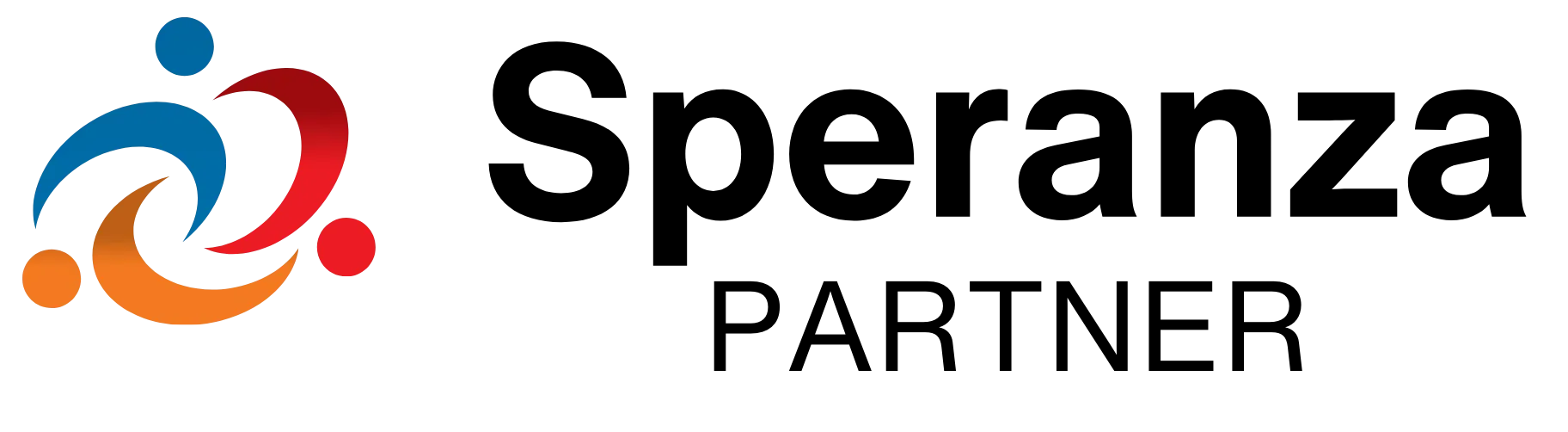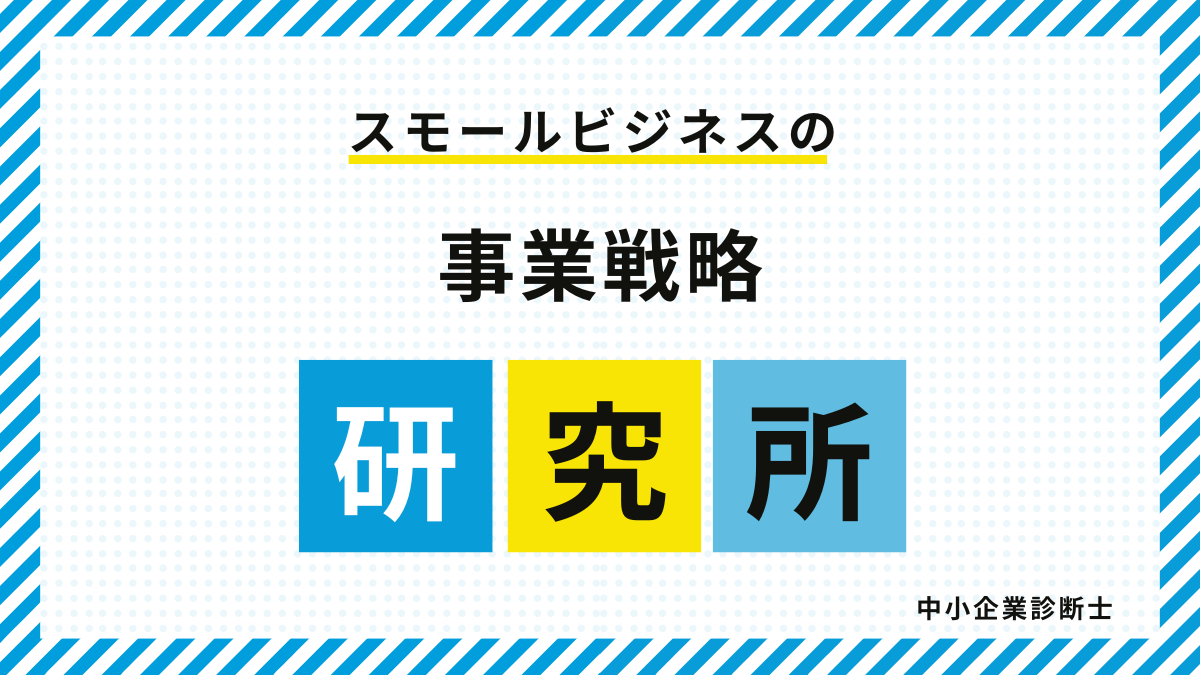
経営者は日々「考える」仕事をしています。事業の方向性を決める、投資の判断をする、社員にメッセージを伝える…。しかし「どのように考えているのか」を意識する機会は、意外と少ないものです。
そこで役立つのが「考え方を考える」=メタ認知です。これは単なる思考力ではなく、頭の使い方そのものを整える技術です。
皆さんこんにちは!事業構想×生成AI活用アドバイザー(中小企業診断士)の津田です。
今回は事業構想を作る作業において生成AIを活用するテクニックの基本的な考え方をご紹介します。
1. 「考える」と「考え方を考える」の違い
- 考える:具体的な課題に向き合うこと(例:新商品の価格設定をどうするか)
- 考え方を考える:自分の思考の進め方や枠組みを点検し、必要なら切り替えること(例:「価格ばかりに囚われているが、顧客体験の視点はどうだろう?」)
この違いを意識するだけで、思考は堂々巡りから解放されます。
2. 経営者に必要な「考える技術」
経営者にとって「考え方を考える」ことは、思考法を選び分けることでもあります。代表的なものを挙げてみましょう。
- ロジカルシンキング:筋道立てて整理し、因果関係を明らかにする。
- クリティカルシンキング:前提を疑い、思い込みを外す。
- ラテラルシンキング:固定観念を外し、発想を飛躍させる。
- デザインシンキング:顧客視点から共感し、課題を発見して解決する。
- メタ認知:今、自分がどの「考え方」で考えているかを意識し、適切に切り替える。
これらを「状況に応じて選ぶ力」こそが、事業構想の質を高めるカギとなります。
3. 事業構想における応用
事業構想を描くとき、経営者は未来を形にしていきます。その際に有効なのが、思考プロセスのメタ認知です。
- 堂々巡りから抜け出す:「なぜこのテーマばかり考えているのか?」と問い直す。
- バイアスに気づく:「成功体験に引っ張られていないか?」をチェックする。
- 視点を変える:「顧客ならどう感じるか? 社員ならどう見えるか?」と立場を入れ替える。
これにより、単なる事業計画書ではなく、本当に実現可能で、共感を得られる事業構想が見えてきます。
4. 実践のための問いかけ
実際に「考え方を考える」力を鍛えるには、日常でこんな問いを投げかけてみましょう。
- 今、私はどんな枠組みで考えているのか?
- その前提は本当に正しいのか?
- 他にどんな方法で考えられるか?
- 相手の立場に立ったら、どう見えるか?
おわりに
経営者にとって「考える」ことは日常ですが、「考え方を考える」ことは戦略です。思考を選び、調整できる力は、激しい変化の時代において、事業構想の強力な武器になります。
次に事業を考えるとき、ぜひ「今、自分はどう考えているか?」を意識してみてください。そこから、新しい視野と可能性が開けていきます。